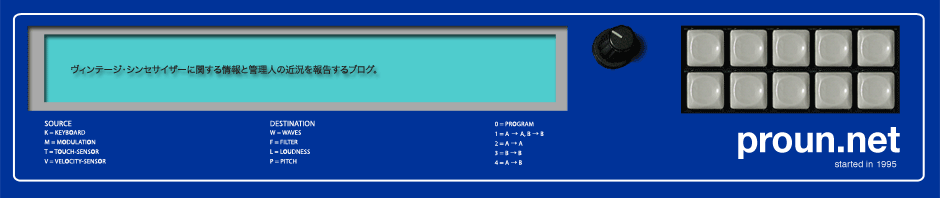東京・上野の東京藝術大学大学美術館で行われているバウハウス・デッサウ展に行ってきました。バウハウスときいてピーター・マーフィー率いるイギリスのバンドを思い出したゴスな方の中にも、その名前がここから来ていることをもしかしたら知らない方もいるんじゃないでしょうか。
東京・上野の東京藝術大学大学美術館で行われているバウハウス・デッサウ展に行ってきました。バウハウスときいてピーター・マーフィー率いるイギリスのバンドを思い出したゴスな方の中にも、その名前がここから来ていることをもしかしたら知らない方もいるんじゃないでしょうか。
とは言っても、バウハウス自体はゴスでもなんでもなく、実は1919年にドイツに開校された建築や工業製品などを目指す造形学校の名前。このバウハウスの存在は建築やデザインの話になると必ずと言っていいほど出てきます。その世界ではとても有名でバウハウスの名前を知らない人の身の回りにもその影響が生活の隅々にまで浸透していると言って過言ではありません。
 たとえば今ではいろんな場所でみかける「パイプ椅子」ですが、スチールパイプで椅子を作るという発想自体、バウハウスのマルセル・ブロイヤーが考え出したものです(写真は彼が発表したワシリー・チェア)。
たとえば今ではいろんな場所でみかける「パイプ椅子」ですが、スチールパイプで椅子を作るという発想自体、バウハウスのマルセル・ブロイヤーが考え出したものです(写真は彼が発表したワシリー・チェア)。
バウハウスのデザインの特徴は、あまり装飾的なことをやめ、シンプルで機能的。すっきりとしたデザインは飽きが来ず、いまでも十分通用する普遍性があります。教師にはカンディンスキーやクレーといったそうそうたる芸術家が名を連ね、卒業生の中にも数人の日本人がいました。
ところがカンディンスキーなどの社会主義国出身者がいたことや、ロシア構成主義の持つ合理主義・機能主義的な影響を色濃く残していたことなどからナチスの圧力が高まり、ワイマール、デッサウ、ベルリンへと移転を余儀なくされたバウハウスは1933年にわずか14年で閉校。この歴史をつづったのが今回の展覧会です。
会場へはデザインや建築に興味のある人や、興味がないけどレポートを書くために見に来た美大生の女の子(バウハウスっぽくなくてケバい)、真面目なドイツ人グループ(建築関係?)、何でも見に来る有閑マダムなど、平日ならではの客層で大賑わい。東京の人って何でも見に来るんだなって感じです。展示物は意外と多く、当時生徒が作った習作から工業製品、家具、建築物のパース、写真、絵画、関連資料などがおなかいっぱい見られました。
結論。やっぱり僕はバウハウスの影響をすごーく受けてます。音楽に関してもそう。イギリスのバウハウスのことじゃなくて、やっぱりああいうミニマリズムとかアブストラクトな幾何学模様とか神秘主義もちょっとあるのが肌に合ってる。一見冷たく見えるんだけど、どことなく有機的で斬新。無難なところで終わらせていない、そこはかとなく芸術性を感じさせる気合いみたいなものががんがん伝わってきました。
バウハウスの影響を受けたという阿佐ヶ谷団地の低層住宅街も見ておきたかったけど、今もう再開発が進んで取り壊されているそうで残念です。でも20世紀初頭の芸術ってやっぱりすごい。
金沢旅行
先月30日には新生9dwの初ライブ(公式には)があり、やっと一息。自宅に帰ってきたのが夜中の1時くらいだったけど、そこから殆ど眠らずに朝6時起きで金沢へ行ってきました(笑)
羽田から飛行機に乗ること1時間。現地へはちょうど昼ぐらいに着きました。
金沢は小京都と呼ばれているだけあって、とても京都に似ていました。古い町並みとファッションビルとうまい食べ物と…。それが京都よりも小さなエリアに全部集まっていて、1カ所で全部回れる感じ。金沢の人はみんな気さくでどこの店に入ってもとても愛想がいい。人口が少ないのでお茶をするにも並ばずに入れるし、テーブルの大きさも大きいし、どこもゆったりとした感覚。いわゆる街のギャルでさえ見た目は東京と比べると随分控えめなメイクでした。
街のあちこちに小川と木があって、自然がとても残っていて、散歩にももってこい。これが繁華街のど真ん中にあるとは思えないゆとりのある環境なんです。
そんな中、川の横の道を歩いていると、40代後半の女性の人が「大変!」と言いながら向こうから走ってきました。川をのぞき込んでいるのでてっきり子供が流されたんじゃないかとあたりは騒然。女性は川下のほうへずっと走っていってしまいました。周囲の通行人も何が何だか分からず川をのぞき込んでいましたが、川の流れは随分速く、何か流されたとしても助けに行ける状態じゃなかったのです。
そんな時、橋の下から「ニャー」という子猫の鳴き声が! みんなは猫が流されたとその時分かりました「あ! 鳴いてる!」みんなどうしていいのかその場の状況を見守っていましたが、橋と水面の間は50cmくらいしかなく、猫はの声はするけど姿は見えない状態。あたりの人はみんな川の中をのぞき込んでいるし、通り過ぎていくおじさんが僕に「何があったの?」ときいてきて、対岸のスーツを着た若い男の子は「こういう場合、どこに電話すれば助けに来てもらえるんでしょうね?」と川越しにしゃべりかけてくる。ほんとにみんな人なつっこいかんじ。
結局子猫は橋の下流に流されたところを助け出されたらしく、一件落着。その状況を知らんぷりしている人なんて殆どいなかったのが印象でした。

ですが金沢の目的はそういう観光ばかりではなかったのです。今回の旅行の最大の目的は、前から計画に入っていた、金沢21世紀美術館でやっている日本初個展の「ロン・ミュエック展」を観に行くことでした。
東京へ来るなら待っても良かったんですが、どうやら金沢だけしかやらないみたいなので、こりゃ行くしかないだろうと思い立ち、今回の旅行に。
ロン・ミュエックはロンドンに住んでいるオーストラリア人で、今年50歳。当初はイギリスの子供向け番組のキャラクターデザインなどを手がける造形クリエイターだったそうですが、近年その技術を生かした超リアルな人体オブジェで注目されるアーティストです。
彼の作品はこれまで発表されたものの殆どが人体、つまり人間を題材にしていて、シリコンで作られたそれはまるで生きている蝋人形のよう。浮き出た血管はおろか、体毛やニキビ、肌の色ムラまでホンモノそっくりなのですが、いわゆるリアルな蝋人形とまったく違うのはその「大きさ」です。体長が5mくらいありそうな新生児やベッドに横たわる女性。まるで見ているこちらが小さなネズミにでもなったような気分です。逆に1mに満たない大きさの「小さな人間」もいて、だけどスネ毛がリアルに生えているのですよ。
どの作品も具体的に今何かをしている人、というようなものは少なく、表情やポーズから見ている側に様々なイマジネーションを起こさせるようなものが多いです。その表情の切り取り方やよく考えると非現実的なシチュエーション(裸でボートに座るオヤジとか)がうまく作品にヒネリを与えているようです。
百聞は一見にしかず、というわけで、you tubeに今金沢に来ている作品とかなりかぶった作品を紹介しているスライドショーがありましたので、ぜひ見てください。
この下のビデオではメイキングも見られます。この手を挙げている妊婦の作品は金沢には来ていませんでしたが、字幕入りのメイキングビデオが会場でビデオ上映されていました。
あとこのスライドショー、画像が鮮明で面白いです。これ必見。
ブルックリン・ミュージアムのスライドショー
雑学:くいだおれ太郎は15体いる!
大阪に行くと必ず観光客が記念写真を撮りに行くあの道頓堀のくいだおれ人形、最近のニュースではあの店が閉店すると言うことで人形がどこへ行くかなんて話題が盛り上がっていました。そこで出てきたのがくいだおれ太郎には父と弟がいるというトリビア。へえー1人だけだと思っていたのに意外〜! みたいな驚きの声があちこちのお茶の間で響いたんでしょうねえ。
ところがちょっとまてよと。僕はずいぶん昔にくいだおれ人形が15体あるという話をどこかできいたことがある。それなのにどこのテレビも取り上げていない。これにちょっと疑問を感じて調べました。
我が家には僕が作った古いモノをいろいろ貼り付けた門外不出(実は恥ずかしくて見せられない)のスクラップブックがあり、もしかするとそこに記事が残っているかもと探してみましたら、ありましたありました。
たぶん20年くらい前の情報誌(おそらく「ぷがじゃ」かな?)の切り抜きで、「街の隠れ家で14体のくいだおれ人形は赤いネオンの夢を見ていた」という見出しのコラム。ちょっと引用させてもらいます。
『「一体いくつあるんですか?」「そうですねェ、15…ですかね」「15ォ!」反射的に15体のくいだおれ人形がズラリ並んで一斉にドンチャカやってる図を頭に描いて狂喜しまった私は、即座に取材を申し込んでしまったのだけど、どうして15もあるのかしら? 「くいだおれの創業は昭和24年。今ではすっかり大阪名物になってしまったくいだおれ人形も創業当初から店頭を飾っていました。はじめの頃は道頓堀ゆかりの芸人さんがモデルでね、アチャコとか金語楼とか…、いろいろ変わってたんですよ。今の顔になったのは30年前くらいからですね。」(中略)で、どうして15もあるのかというと…「万博のとき会場に16店出店する予定だったんです。それで16つくったんですが、結局、協会の方が店頭に人形を置いてはいけないと言ってきまして、使わなかったんですけど…」今は交互に修理しながら一人ずつ店頭でお勤め。「ゴールデンウィークは実験的に二つ置いてみたんですよ。」なんて、面白いじゃない。そのあと倉庫へお伴して14の眠る人形ともゴ対面。』
この記事の中には今では語られていない情報がいくつか入っています。まず人形の顔のモデルが当初から創業者・山田六郎氏の顔ではなかったこと。そして15体も人形が存在し、店頭に出ているくいだおれ太郎は修理のためにこっそりと別の兄弟にすげ替えられている可能性があることです。古い人形を処分したという話も聞いたことがないことから、これは意図的に隠された事実なのかもしれません。15体もあれば閉店後の行き先は複雑になるし、なによりそんなにたくさんあることが知られれば希少価値の問題にも影響があるかもしれませんしね。たった1体と思っているから珍重されているということも考えられます。
もうひとつ疑問があります。1970年の大阪万博16店出店のために16体作ったと。それなら道頓堀の本店のために1体必要なはずで、都合17体あったはずです。なのに16体としている。しかも関係者は「15体」と言い、1体が店先に出ているので倉庫には14体あるとしています。であれば1体か2体いなくなっちゃったわけですよね? これどういうわけでしょうか?
切り抜きの記事には倉庫の写真があり、5〜6体のくいだおれ人形が並んでいる様子が撮影されています(顔が紙のようなもので覆われている個体もあり)。父と弟どころか、実は大家族だったことは明白なのです。
どうですかこの雑学? 誰かにしゃべって自慢してください。
追加雑学:「くいだおれ」という言葉は大阪人にグルメ好きが昔から多かったことから由来していると思われていますが、江戸時代、川と堀が多かった浪速(なにわ)の街では橋梁工事のために寄付をすることが成功した大阪商人のステータスで、そこに見栄を張って金を使いすぎて店がつぶれてしまいそうになることを「杭倒れ」といったことがのちになって「食い倒れ」と解釈されるようになったとのことです。
Moogのエレキギター
あのMoogからエレキギターが発表されました。と聞けばギターシンセかなと思いますよね? ところがなんと普通に弦の振動をピックアップで拾うみたいです。普通と違うところは、サスティンの長さをギター側で調整できるほか、勝手にミュートしたり、モノフォニックにしたり、ギターそのもののトーンも大幅に変えられるとか。しかもお値段は70万円くらい…。
メーカーのトップページでルー・リードが試奏している映像があるので見てください。
http://www.moogmusic.com/
ARP Odysseyのケース

ARP Odysseyのケースを特注で作りました! どうですか、サイズもぴったり。上蓋を外せばそのまま演奏できるように仕上げてもらったので、これでどこでも運べるようになりました。Odysseyはつまみがメキシコ製のボロいのを使っているので(このパーツがなかなか手に入らない)持ち運びには気を遣うものなんですが、このケースだと上蓋が本体の端を押さえ込んでケースの中でグラグラしないようにしてくれるので、ケースごと立てても大丈夫だし、寝かせてもゴム足が付いています。素材はいいケースに使われるFRPですが、知り合いに紹介してもらった業者さんに頼んで、自宅に採寸までしに来てもらったのに33,000円でできました。僕と同じMark IIなら図面が既に業者さんが持っているので欲しい方、紹介しますよ。
9dwライブ
やってなかったけど告知。6月30日に渋谷O-WESTで行われる9dwのライブで僕がキーボードで参加させてもらいます。決してうまくはないですが、この1ヶ月くらいはこつこつと練習を重ね、なんとか与えられたパートはこなせるようになってきました(殆どがエレピのパートではあります)。
30日のステージでは愛機ARP Odysseyも持ち込んで鳴らしますよ。もしお時間ある方遊びに来てくださいね。
http://shibuya-o.com/category/west/
以下は9dwのサイトです。サンプルも聴けます。
http://www.myspace.com/9dw
LinnDrum II
 発表からしばらく経ちますが、まったく発売される気配のないLinnDrum II。開発は進んでいるが、写真とはデザインが若干変わるとのことで、発売が予定より延びているそうです。
発表からしばらく経ちますが、まったく発売される気配のないLinnDrum II。開発は進んでいるが、写真とはデザインが若干変わるとのことで、発売が予定より延びているそうです。
オフィシャルのサイトからの情報とパネルのデザインからわかる範囲で書きますと、まずLinnDrum IIはデジタルバージョンとアナログバージョンの2種類が発売されるとのこと。ロージャー・リンとデイヴ・スミス(Prophet 5の開発者)のコラボで、デジタルのほうがロージャー・リン・デザイン社から、アナログのほうがデイヴ・スミス・インストゥルメンツ社から発表されるようです。
予定価格はデジタルが1400ドル、アナログが1800ドル。デジタルは32ボイスでアナログは4ボイスとのことです。
気になるのはやっぱりアナログのほうだと思いますが、つまみはすべてロータリーエンコーダー、1ボイスあたり2オシレーター仕様です。TR-808のようにキックとかスネアとか音によってチャンネルが決められているのではないようで、WAVEFORMというつまみでいろいろ選択できるようになっているようです。フィルターにはローパスとハイパスの2つが同時に使用でき、どちらにもレゾナンスが付いていることから結構過激な音も作れそうです。歪み系のつまみもあります。エンベロープはアタックやディケイが自由に設定でき、そのへんは打楽器系の音に適したパラメーターが付いているようです。出力も4ボイスなので4つあるみたいです。
プログラムの仕方はMPCタイプ(リアルタイム)とTR808タイプ(ステップ)が選択可能。もちろんリアルタイム時にはクオンタイズ等も可能です。
ライブで使用することにも力を入れているようで、プレイしながらいろんなつまみをいじれるようにしているようです。パッドもタッチセンス付きで、見るからにAKAIの製品にぶつけてきている感じです。
さて、肝心の音ですが、どこを探しても見あたらなかったのでなんともいえません。しかし最近のデイヴ・スミスが発表している一連のシンセサイザーにはハズレがないので、結構期待できるんじゃないでしょうかねえ?
立体音響
人間の耳は左右に1つずつ付いているだけですが、これは音がどの方向から聞こえているものなのかを判断するためですよね。でもその二つだけで上下感や前後感をどうやって判断しているのか、これについては完全に解明されていないようです。
通常、オーディオの再生装置には2つペアになったスピーカーやイヤホンが付いていて、その二つからはまったく別な音が送られています。もし両方のスピーカーからまったく同じ音が出ていた場合、人間の耳にはスピーカーとスピーカーの間の真ん中から音が出ているように感じますが、左右が違っていればそうは聞こえません。微妙に左右がずれることでいわゆる「立体感」が生まれ、広がりのある音として楽しめるようになっているわけです。
でもスピーカーやイヤホンで音を聞いていても「前後感」や「前後感」なんて普通感じませんよね?これが今日の本題。
日常の生活では背後から自分の名前を呼ばれれば後ろを振り返ります。ちゃんと後ろから音がしてきたことを知覚できたからです。天井のエアコンがうるさい音を出していればそれもちゃんとわかります。単に「聞こえている」のではなく、聞こえた音からその方向性に関する三次元的な情報を得ているというわけです。不思議ですよね。それがCDを聴いていて感じないのは、根本的に生音と録音された音に「違い」があるからです。
バイノーラル
 人間が生音を聞く条件と同じ条件で録音すれば、あの立体感が録音できるのでは? という発想はずいぶん前からありました。その代表格が「バイノーラル」というものです。人間の耳は頭の側面に付いていて、音の入り口にはいわゆる「耳」とよばれる飛び出したものがついています。人間はこの頭蓋骨や耳を回り込んできた音を聞いているわけです。ではということで、人間の頭部の模型(ダミーヘッド)を用意し、人間の耳と同じ位置にマイクを埋め込んだもので録音できるような装置が開発されました(写真はノイマンのKU100)。これで録音されたものはいわゆる「立体音響」になっています。実際の耳で聞いた感じに近い臨場感があります。しかし前後感や特に上下感の再現には乏しいものがあり、完全には再現されていない方式ではあります。
人間が生音を聞く条件と同じ条件で録音すれば、あの立体感が録音できるのでは? という発想はずいぶん前からありました。その代表格が「バイノーラル」というものです。人間の耳は頭の側面に付いていて、音の入り口にはいわゆる「耳」とよばれる飛び出したものがついています。人間はこの頭蓋骨や耳を回り込んできた音を聞いているわけです。ではということで、人間の頭部の模型(ダミーヘッド)を用意し、人間の耳と同じ位置にマイクを埋め込んだもので録音できるような装置が開発されました(写真はノイマンのKU100)。これで録音されたものはいわゆる「立体音響」になっています。実際の耳で聞いた感じに近い臨場感があります。しかし前後感や特に上下感の再現には乏しいものがあり、完全には再現されていない方式ではあります。
ホロフォニクス
アルゼンチンの脳生理学者ヒューゴ・ズッカレリ氏が1970年代に開発した「ホロフォニクス」というシステムは当時大きな話題を呼びました。彼の開発したシステムで録音された音はかなりはっきりとした前後感や上下感が再現できていて、バイノーラルにはない、異常にリアルな「空気感」をも再現しました。立体音響ブームに火を付けたのが彼の存在です。
彼はシステムの根幹をなす原理を知られたくないために特許も出願していないようで、いまだもって謎なのですが、その徹底した秘密主義からよりホロフォニクスの神秘性が強調されるようになってしまいました。
少ない情報によると、彼が注目したのは「耳音響放射」と呼ばれる現象です。それまで人間の耳は外部の音を聞くための機能しか持っていないと考えられていましたが、近年の研究によると耳の細胞自体が振動することによって「耳自体が音を出している」ということが分かっています。僕は専門家ではないのでこの説明は正しくないかも知れませんが、この耳音響放射が外部から入ってきた音と混ざり合うことで何らかの干渉が起き、そこから三次元的な情報を得ているというのです。それを電気的に再現したものがホロフォニクスというわけです。
ホロフォニクスで録音されたカセットテープやCDは80年代に書店でブックレットを付けて販売されていましたが、通常のCDなんかよりも高い値段で販売されており、買った人はさほど多くはなかったと思います。今でもネットオークションでは高値で取引されていますが、内容は効果音集のようなもので、もう一つはピアノ曲を集めたものがあります(これはいまひとつ効果がわからず)。
ホロフォニクスを使った音楽CDも少ないですがあります。一般的に知られているものではマイケル・ジャクソンのアルバムBADに使われている効果音とか、ピンク・フロイドのFinal Cutに一部使用されているのが有名ですが、極めつけはイギリスのSome Bizzareというインディーズ・レーベルから80年代に作品を数多くリリースしていたサイキックTVというバンドの1stと2ndアルバムです。この2枚のアルバムは全面的にホロフォニクスで録音されており、特に2ndアルバムには「このアルバムはマイクロフォンを一切使っていません」と但し書きが書かれているほど手の込んだ立体音響を聴かせてくれます。
Psychic TV
僕はホロフォニクスの存在を知る前からサイキックTV、というかSome Bizzareのファンでした。当時そのオフィスはロンドンのSOHOにあり、スタッフも5人程度の弱小レーベルではありましたがTHE THEやSOFT CELLなどの100万枚単位でアルバムを売った売れっ子アーティストをかかえていたためにかなり羽振りのいいレーベルでした。その金をそんなに売れるとは思えないサイキックTV(前身はスロッビング・グリッスルというインダストリアル・ノイズの大御所)につぎ込んだことでホロフォニクスのような特殊な環境でアルバムを作ることができたようです。
1st “Force The Hand Of Chance”は非常に泣き泣きのアコースティック・ギターにボーカルのジェネシスPオリッジ(男だが現在は豊胸手術して両性具有者に…)がヘナヘナの声で歌い、そこで美しいストリングスが入ってくるわけですが、はっきりとした三次元の感覚があるとはいえず、ただ「良く録れた録音」といったイメージしかありません。その後怒濤のギターノイズへ突入し、非常に宗教じみた音楽世界になっていくのですが、ところどころに非常に立体的に聞こえる曲もありますが、ホロフォニクスの醍醐味を味わうにはちょっと物足りないです(アルバムとしては僕は最高だと思いますが、殆どの人はついて行けないと思います)。
 1stの立体感の欠如の問題がオーバーダビングにあったことを反省し、再度トライしたのが2ndの”Dreams less Sweet”です。これは曲間にも非常に立体感の強調されたホロフォニクスな効果音が満載で、曲全体にもその良さが現れています。全面ホロフォニクスで録音されただけあって、特にヘッドホンで聴くとおお〜っと感動します。ただキャッチーでわかりやすい音楽が好きな人には相当キツい音楽でしょう。ジャケットの花の写真の花心に合成されているのがジェネシスのポコチンに入っているリングピアスであることを考えれば、内容もお察しできるかと思います。美しくも宗教的で病的、ノイジーで神秘主義みたいなグループです(ちなみにリーダー兼ボーカルのジェネシスPオリッジは「イギリスで最も病んだミュージシャン」として国会でも取り上げられたことがあるとか。まー豊胸とかしてますしね)。
1stの立体感の欠如の問題がオーバーダビングにあったことを反省し、再度トライしたのが2ndの”Dreams less Sweet”です。これは曲間にも非常に立体感の強調されたホロフォニクスな効果音が満載で、曲全体にもその良さが現れています。全面ホロフォニクスで録音されただけあって、特にヘッドホンで聴くとおお〜っと感動します。ただキャッチーでわかりやすい音楽が好きな人には相当キツい音楽でしょう。ジャケットの花の写真の花心に合成されているのがジェネシスのポコチンに入っているリングピアスであることを考えれば、内容もお察しできるかと思います。美しくも宗教的で病的、ノイジーで神秘主義みたいなグループです(ちなみにリーダー兼ボーカルのジェネシスPオリッジは「イギリスで最も病んだミュージシャン」として国会でも取り上げられたことがあるとか。まー豊胸とかしてますしね)。
また長らく廃盤になっていた2ndのCDが今月に入って突然デジパックで再発されました。欲しい人はなくならないうちに買っておかないと、またヤフオクで法外に高い値段で買わなきゃいけなくなりますよ。あ、ちなみに1stは日本盤のみ初回のボーナス盤もCD化されましたが、これは今もって廃盤です。中古で出ても非常に高いです。
Psychic TVやホロフォニクスについて詳しく知りたい方は非常に良くできたサイトが日本に存在します。23net.tvのここをご覧ください。
下戸遺伝子
自慢にもならないけど、僕は基本的に酒が全然飲めない人間なのです。「飲まない」と「飲めない」は全然違うわけですが、僕の場合は「飲めない」というタイプのほうだと思います。どういう感じかというと、ビールはコップ一杯がいいところ。基本的に苦いもの好きなのでビールの味は大好きだし、他の酒も大好きなので、結構飲めれば飲んでいたかも知れないけど、まー飲めないわけです。
今から3万年ほど前に中国大陸のどこかでアルコール代謝物アセトアルデヒド(毒性強い)を酢酸に分解する酵素を作り出す遺伝子に突然変異が起きた人が生まれ、その遺伝子がどんどん広がっていきました。白人や黒人には見られない、モンゴロイド系民族だけに見られる酵素欠損型遺伝子は、中国内陸部では1〜2割の人が持っているそうです。僕もその遺伝子を持っているということです。先祖は遠いどこかで大陸につながっているということなんでしょうね。というか、日本人なら誰でも大陸に先祖を持っているんでしょうけど。
日本ではこの酵素欠損型遺伝子を持っている人が一番多く分布しているのは関西地方で、そこから東西に離れれば離れるほどこの遺伝子を持っている人は少なくなっていくそうです(沖縄とか東北にはお酒の強い人が多いですよねー)。
これは朝鮮半島や中国大陸から渡ってきた渡来人が支配していた大和朝廷が関西にあったことと深く関係しているらしく、つまりそのへんで「混血」がおこったわけです。北方民族だった弥生人の特徴を色濃く持った僕の体は(しかも関西出身で…)、もろにこの先祖を持つ典型と考えて良さそうです。渡来人との混血によって日本人の遺伝子にもこの「下戸遺伝子」が現れ、僕のようにアルコールを受け付けないかわいそうな人たちが生まれる羽目に…。
ヤマタノオロチ伝説は大蛇に見立てた渡来人の襲来をヤマト民族が酒を飲ませて退治した話だという説がありますが、やっぱりヤマタノオロチも僕と同じ酵素欠損型遺伝子を持っていたんでしょうねー。
ちょっと話はそれますが、邪馬台国の「邪馬台」って皆さんは学校で「ヤマタイ」と読むように教わりませんでしたか? でもこれを「ヤマト」と読む説は以前から多くあるんですよ。学校では教えてくれませんけど。
邪馬台国の話の200年後ぐらいには「ヤマト」と名乗る場所が都市になっていたわけですから、これを「ヤマト」と読んで「何か関係があるのかなあ」と考えるのが普通と言えば普通でしょうけど、あえてこれを「ヤマト」と読んでこなかったところに過去の日本古代史の学者達の作為を感じます。これをヤマトと読んでしまうということは、要するに邪馬台国九州説が大きく後退することを意味するからです。
「ヤマト」の「ヤマ」は山の意味で、「ト」は「瀬戸」の「戸」や河戸の「戸」と同じ意味だとする説があります。奈良以外に九州にも「山門」という古い地名があって、ここが邪馬台国の候補地にもなっているわけですが、山があるところに「ヤマト」という地名を付けて読んでいたのが当時のよくある習わしで、それが地名として残ったとするなら、九州にも奈良にもヤマトがあるのは特に不思議はないような気が僕個人としてはします。もちろん僕は大学に行ってこういうこと研究したんじゃなくってただ本を読んでいるだけなんですけどね。あんまり本気にしないでくださいよ、素人の言っていることを。
でも日本語のルーツって面白いですよね。そこに一番興味があったりして。
追伸。
僕が弥生人の特徴を色濃く持っていると書きましたが、現代の日本人はもともと日本に住んでいた縄文人と大陸から渡ってきた弥生人の混血なのですが、どちらかの特徴が色濃く出てしまう人も結構いるみたいです。僕がそれ。
弥生人は元々北方民族で、寒い地方で暮らすために有利な特徴を備えています。身長は縄文人より高めだけど、顔の骨格は細長く目は一重で鼻も低く出っ張りが少ない醤油顔。歯が大きく前歯がシャベル状。耳垢は乾燥しているんだそうです。全部僕だ(笑)。手足も短いのは日本人の殆どの人が持っている特徴ですね。でも僕は天パで、これは弥生人の特徴じゃない。どっかから来た別の遺伝子でしょうか。
一方縄文人は背はやや低め。顔面の骨格はがっしりしていて、毛深い。いわゆるソース顔で濃い顔。歯が小さく、耳垢は湿っています。今風な感覚で言えば縄文人のほうがモテるかも。遺伝学的には弥生人も縄文人もほぼ同じなんだそうですが、見た目が違う以上、何か違いはあるんでしょうね。優劣とかじゃなく。さてみなさんはどっちですか?
さらに追記。
2001年のDNA調査によると、縄文人の直接的な祖先はバイカル湖畔に住むブリヤート人というモンゴロイド系の民族だった可能性が高いことがわかりました。これまで言われてきた、縄文人は南方系、弥生人は北方系という分け方は正しくなく、どちらも北東ユーラシアから入ってきたとするのが最新の結論。もちろんいろんなところから様々な民族が流入してきた日本においては祖先を一つに絞り込むこと自体ナンセンスだと言えると思いますが、ブリヤート人との共通点は意外というか、事実としてそれはあるんでしょうけど、ブリヤート人のDNAを受け継ぐ民族は中国や朝鮮半島にもたくさんいることでしょうから、特に驚くことではないのかも知れませんね。ちなみに耳垢が乾燥しているのもこのブリヤート人が持つ突然変異の遺伝子と関係があるのだそうです。しっかり僕が受け継がせていただいています。
データのバックアップ
たまったデータ、焼いてますか?
DAWで音楽を制作した場合、マスターテープはそのセッションファイルと言うことになります。ちょっとしたトラックを重ねていけば1曲のサイズが3GBくらいいっちゃうことなんてよくある話で、ドラムとか録音すれば10GBなんてことにもなりかねません。最近のハードディスクは最低でも320GBくらいはありますが、100曲でいっぱいになるとなればさほど大きなサイズとも言えないのではないでしょうか。
そこでもう使わないけど保存しておきたいデータは徐々にバックアップしてハードディスクから消していくという作業になりますが、みなさんはどうしているでしょうか?
ハードディスク
バックアップなんてとらずにハードディスクが一杯になったら新しいハードディスクを買う! そんな人は結構多いです。最近のドライブは一昔前から比べると格段に信頼性も上がっていて、そのまま置いていても壊れることは少なくなりました。価格も安くなり、メガバイトあたりのコストは一番安いのが何を隠そうハードディスクです。でも飛んだ時はデータが全滅するリスクを背負っています。これはある意味賭けです。
DVD-R
ごく一般的なのはDVD-Rに残すという方法です。4.7GBで100円もしないし、ドライブもMacやPCに付いているか、あとから買っても1万円台。書き込みも速い。これは使えるメディアです。
しかし欠点もあります。まず長期保存に不安が残ること。もともと光に反応する有機的な色素がベースになっているため、光学メディアは保存の仕方が悪ければどんどん劣化していきます。たいしたデータじゃなければ問題ありませんが、確実に保存する方法としては心許ないメディアかもしれません。
もう一つは大きさ。「1枚に4.7GBも入る」という言い方もできますが、「4.7GBしか入らない」という言い方もできます。1枚に数曲分のセッションしか入りませんのでアルバム1枚分を1枚に納めるのは無理で、データを複数枚に渡らせる上、DVD-Rが100枚にもなると結構な量になります。増えれば今度は欲しいデータを探すのに苦労します。
DDS
データ専用の4mmDATテープカートリッジを使い、データをバックアップする規格で、DDS専用のドライブが必要になります。メディアの見た目はDATと全く同じなためコンパクトで比較的大容量のデータを収納できます。歴史も古く、磁気テープというメディアの性質に不安を持たれる方も多いかも知れませんが、案外安定していてDVD-Rなんかよりもむしろ信用できると思います。
DDSには容量の小さい方からDDS1,DDS2,DDS3,DDS4,DDS5,DDS6と6種類あり、ドライブは上位互換になっていて、カートリッジの種類がそれぞれ違います(見た目は同じ)。
問題はドライブ本体のコストで、DDS6のドライブを新品で買うと15万円とかしちゃいます。もともとサーバーで使われる業務用の規格なのでそうなっているのですが、実は中古になるととたんに安くなります。ネットオークションではDDS4の中古外付ドライブが6000円くらいです。世の中的には既に時代遅れと言われているDDS4ですが、僕はドライブとメディアのコストパフォーマンス(CP)からDDS4が今でも大本命だと思っています。メディア1本で20GB(非圧縮)とれて価格は安ければ800円くらい(カメラ量販店だと1300円くらい)。DDS5はメディアの価格はが倍ですが、容量は倍とはならず、36GB程度。ドライブは外付けの中古で15000円前後といったところでしょうか。DDS6は正直なところ、音楽で使うにはCP面からも躊躇します。
難点はDDSドライブの接続フォーマットが基本的にSCSIだけだということです。最近USB2.0で動作するものも発売されましたが、中古では出回らないので実質的に使えません。今でもSCSIカードをPCに差している人なら問題はないでしょうが、今時SCSIを好きこのんで使う理由もほとんどなくなってきました。そこでSCSIをFireWireに変換してみようとする僕の試みについてちょっと書かせてください。
DDSでバックアップを取る方法(FireWire / IEEE1394編)
日本のラトック社が出しているFireRex1は僕の知る限り唯一の、UltraSCSI機器をFireWire接続させてくれる変換器です。発売から何年も経ちますがまだまだ現行機種で、古いSCSI機器を現代のMacやPCで動かすためにはなくてはならない装置です。
これを使えばDDSドライブをSCSIのないMacintosh G4などで動作させることが可能ではないかということで、最近うちでもテストを始めました。
基本的にDDS3までは50pinですが、DDS4以上は68pinのUltraWideSCSI仕様です。SCSIも上位互換規格のため、68pinを50pinに変換するアダプタさえあればUltraSCSI対応のFireRex1を使うことはできるはずです。
しかしFireRex1を使うにはまずドライブが対応しているかどうか確認が必要です。対応表に乗ってない機種はだめかというとそういうわけでもなさそうですが、後述するとおり、何かときをつけなければならないこともあります。
まずOSXもWIndowsXPでさえもOSでDDSドライブをサポートしていないため、ドライブを動かすためのソフトが必要です。Windowsではいくつか選択肢がありますが、Macだと選択肢はぐっと狭まります。事実上EMC Retrospect Backup 6.1が標準で、ラトックのサポートの方から教えてもらったBRU LE(ブルLE)for Mac OSXという手が若干残されている程度です。
Retrospectは対応ドライブが非常に多く、インターフェイスも洗練されていますので何も問題が起きなければオススメできるソフトです。差分バックアップができるので、バックアップ後にセッションファイルに手を加えてオーディオトラックが増えたとしても、再度同じテープにバックアップすれば、増えたり変更した分だけバックアップしてくれます。
BRU LEは若干価格が高く、インターフェイスもMacらしくないのですが、操作は簡単です(デモ版でしか使ったことがない)。
DDSのもう一ついいところは、DVD-Rと違ってメディアの交換回数が少なくてすむので夜中に回しっぱなしで寝ることができるということです。バックアップが終了するとコンピュータを終了させることもソフトでできます。DDS4でだいたい120〜140MB/分くらいのスピードでバックアップがとれますので検証なしなら1本3時間程度。スピードの面ではDVD-Rに劣っているでしょうけど、ほったらかしにできるというのは魅力じゃありませんか?
ちなみにDDS4はドライブ本体にファイルを圧縮するハードウエアエンジンを搭載していますが、本来であればこの機能を使うとファイルサイズが半分になり、1本に40GB分を記録できます。しかし残念なことにオーディオファイルはデータの性質上圧縮しても殆ど小さくならず、20GBのままです。
話は戻ってFireRex1ですが、僕のテストでは時々不安定になることがあり、その問題の大半がFireWire400と800の混在であったことが判明しました(前日の記事を参照)。SCSIを使った方が安定しているようではありますが、FireWireでのテストもさらに重ねてまた報告したいと思います。
LTO(Ultrium)
DDS4を中古で買えという話ついでにいうと、もうひとつ気になる規格があります。Ultrium(ウルトリウム)という名前で呼ばれている、これまたサーバーのバックアップ専用マシンの規格です。LTO1、LTO2、LTO3、LTO4とあるのですが、一昔前のLTO2でも1本のメディアに非圧縮で200GBも入り、メディアの価格も5000円程度です(LTO3なら400GBで1万円程度のカートリッジが使えます)。ランニングコストはDDS4やDVD-Rより上です。専用のテープカートリッジを使いますが、信頼性も非常に高く、安心してバックアップできます。
問題はドライブが高いことです。しかしLTO2なら既に十分「型落ち」ですので、外付けドライブでも運が良ければ3万円程度で買える可能性もあります。ただしまたこれもSCSIなんです。DDS同様対策が必要です。ちなみにRetrospectはUltriumドライブにもかなり対応しています。興味があったら調べてみてください。
Blu-Ray
最近DVD-HDに勝利したBlu-Rayですが、ドライブの価格が安い物で4〜5万円、メディアが1層で25GB記録でき、量販店で1500円程度です。ドライブがやや高めですが、ランニングコストはDDS4とさほど変わらず、ドライブの価格が下がってくればDDS4よりCPが高くなることは必至です。
以上、長々とバックアップのフォーマットについてふれてみましたが、なにげにDDS4は安くていいなというのが今のところの僕の結論です。ですが、1年もしない間に事態が変わる可能性はあります。それがこのバックアップ業界の宿命なのです。