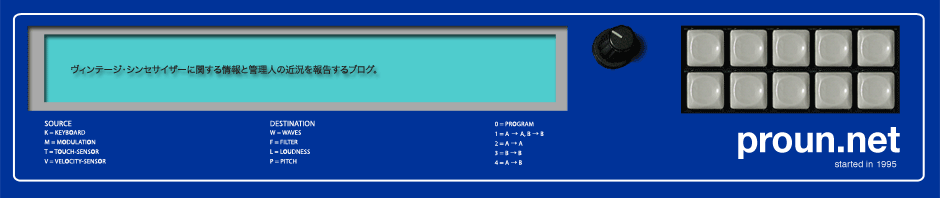「発明家」といえば日本ではエジソンかドクター中松しか知られていないけど、エジソンが生きていた時代にエジソンを超える発明をしていたのがニコラ・テスラ。高校生時代の僕のヒーローだったなあ。
エジソンが電球やレコードなど僕たちの生活に密着した発明が多かったのに対して、ニコラ・テスラが発明したのは無線送電システムや無線ラジオなどデカいものが多い。だけど蛍光灯なども彼の発明で、社会的に貢献した発明も多いです。ところがある時期から地震発生マシンの開発や、地球をまっぷたつに割るシステム、あげくの果てには宇宙人との交信をはじめ、世間の人たちをドン引きさせていて、サブカル好きの間ではマッド・サイエンティストとして知られている。でもね、そのぶっ飛び具合がね、僕のツボにはまっている。一般人の目をひくようなキャッチーさはないけど、いわゆる天才的な能力を持っていて、なおかつ狂ってる。この人最高。
そんな彼ですがエジソンのもとで働いていた時期もあって、エジソン・リスペクトだった。エジソンは自分で言っていた名言どおり99%の努力でできているような人で、他人の理解を超えた頭脳を生まれつき持っていたテスラとは対照的です。
結局彼はエジソンのもとを去り、彼のライバルへとなっていく…。電力会社への発電機の売り込みに至ってはエジソンが考えた直流式とテスラの考えた交流式が競争するはめになり、最終的にテスラの発電機が採用されたというエピソードがあるくらい。この際、テスラは交流の方が人体にも安全だということをアピールするために高圧電流を自分の体に流すというデモンストレーションをやったとも言われています。クールだぜ、ニコラっち! 今僕たちの使っている100Vの電気が交流なのも、この時のテスラの頑張りが利いてるんですよ。
そんなテスラの考えたものの一つに「テスラ・コイル」というものがあります。これ、実際に動いている映像見るとすごいですよ。ビジュアル的にもいいし、音もいい! だけどこんなの何に使うんだろ?いや、そんなことニコラに求めても意味ないです。とりあえずインパクトで勝ってます。
「未分類」カテゴリーアーカイブ
楽しい電子楽器 自作のススメ

Wiiリモコンをミキサーに入れる。
Youtubeの画面、横長になりましたね。
伝説の4人衆。
またデザイン変更。
丙午(ひのえうま)

石田徹也
 以前から気になっていた画家がいて、いつか作品を見たいと思っていたのですが、東京でほとんど見る機会がなかった石田徹也。その個展が都内では初めて大々的に開かれるというので練馬区立美術館へ行ってきました。
以前から気になっていた画家がいて、いつか作品を見たいと思っていたのですが、東京でほとんど見る機会がなかった石田徹也。その個展が都内では初めて大々的に開かれるというので練馬区立美術館へ行ってきました。
デザイン変更
大琳派展
琳派、行ってきました。もちろん目玉は風神雷神図屏風。俵屋宗達が描いたものを100年後くらいに尾形光琳がカバー(?)し、それをまた酒井抱一がカバーしたという屏風絵で、つまり違う人が描いた同じものが3つあります。今回の上野で行われている大琳派展ではなんとその3つを同時に展示しているのです。一つでもなかなか本物が見れないのにこれは3つの違いを比較できる絶好の機会。

写真は俵屋宗達のオリジナル。実際に現物を見たのは今回が初めてだったけど、間近で見ると案外筆致が荒い。勢いで描いている感じ。だけど配色とかモチーフの配置が絶妙で、絵の構成自体は勢いで描いたとは思えなかった。すごく考えに考え抜かれたかんじ。なのに筆の運びが非常に勢いがあって、あるいみロック的なざっくり感がある。「オラー!」という意味のない気合いが絵から聞こえてくる感じ。これは国宝になってるのもわかるぶっ飛びの名作ですね。
この絵は京都の建仁寺が持っているのですが、宗達は京都の町絵師だったので京都に伝わったのです。ところが明治に入るまで宗達の評価はずっと低くて、おかげで目利きのアメリカ人に代表作の多くを買われてしまい、海外に流出しました。宗達の絵は斬新すぎるんです。宗達は町絵師でしたから発想が自由で、しきたりに縛られずにエクスペリメンタルな部分を持っている作品も多いですが、当時から一流の絵師としての評価を受けていたようです。なのに生没年は不明。

これは尾形光琳。宗達の絵をカバーしたわけですが、完コピかというとそうでもなく、色や顔の描き方をあえて微妙に変えています。左手の雷神は宗達は太鼓の輪を枠からはみ出すようにしていますが、光琳はそれでは安定感がないと思ったのか、もっと内側に寄せています。もともと宗達の作品は不安定なのがいいのに、そのへん光琳は違ったみたいです。改良しているところからすると、宗達の絵はいいけど完璧だとは思っていなかったってことでしょう? 自信もあったのかもしれませんよ。宗達リスペクトではあったんですけど。
光琳は実家が金持ちのボンボンで結構遊び人だったみたいですが、ボンボン特有の品の良さと都会的なセンスがあって、そこが今でも受けている所以です。ただ確かに絵もうまいんだけど、宗達のような何ものにも左右されない自由な気風という部分ではやや劣るし、後述する酒井抱一のような緻密な描写力も持っていません。だけど光るセンスがあって、感覚的にはすぐれたものを持っていたのがわかります。ぱっと見のキャッチーさもあります。洗練されているんです。

酒井抱一のは宗達のではなく、光琳の絵を見て描いたので宗達の孫コピーですね。より安定感を増した感じ。絵もうまい。色も鮮やかだけど、色遣いは光琳のほうが好きかな。タッチも軽やかで、なめらかな動きの見える描写というわけではなくて、むしろ形式化された風神雷神図のデザインを完璧に仕上げようと言う気持ちが絵からにじみ出ている。今は黒く酸化している銀泥混じりの雲も光琳はたっぷりとバランスよく入れている感じがするけど、抱一は重くなるのを嫌っているようにも見える。屏風の折り目をモチーフがまたぐように描いているのも宗達や光琳とは違う点。でも酒井抱一は絵がうまい。まじめに勉強してきた感じがします。植物を描いてもボタニカルアートみたいだし。こういう動的なモチーフはよくないかもしれないです。
結論。僕は俵屋宗達が3人の中で最も好きです。やや社交性のない、こもったセンスもあるけど、内なるパワーをめらめらと燃やしているような爆発力も秘めている、そういう表に見せないエネルギーを感じます。これは音楽の趣味とも共通しているところではあるけれど。